犬は私たちにとって家族同然の存在です。その大切な命が尽きたとき、深い悲しみに襲われるのは当然のことです。しかし、感情的に辛い中でも、やらなければならないことがあります。本記事では、犬が亡くなった際の心のケアと実務的な対応方法について、我が家の経験も踏まえて詳しく解説します。少しでもあなたのお役に立てれば幸いです。
Contents
1. 犬が亡くなった直後にすべきこと
1.1. 落ち着いて状況を確認する
愛犬が亡くなる瞬間に立ち会うことは、飼い主として非常につらい経験です。しかし、まずは深呼吸して落ち着き、本当に亡くなったのか確認しましょう。
- 呼吸や心拍が止まっているか。
- 瞳孔が開いているか。
これらを確認することで、次の行動を冷静に考えることができます。
1.2. 動物病院への相談
もし動物病院に通っていた場合は、担当の獣医師に連絡を取りましょう。犬の火葬を行う際、基本的に獣医師による死亡診断書は必須ではありませんが、死亡診断書が必要になる場合もあります。また、病院によっては遺体の取り扱いや火葬業者を紹介してくれることもあります。
1.3. 死亡診断書の要否
死亡診断書が不要な場合
✅ 一般的なペット火葬業者を利用する場合
→ ペット専用の火葬業者や移動火葬サービスでは、死亡診断書なしで対応してくれることがほとんどです。
✅ 自治体のペット火葬を利用する場合
→ ほとんどの自治体では死亡診断書なしで受付可能ですが、一部の自治体では「死亡届」の提出を求められることがあります。
死亡診断書が必要な場合
📝 保険請求をする場合
→ ペット保険に加入しており、保険金の請求をする際に死亡診断書の提出が必要になることがあります。
📝 自治体によっては求められる場合がある
→ 自治体の公営火葬場を利用する場合、死亡診断書や死亡届を提出しなければならないケースがあります。
1.3. 家族や親しい人への連絡
家族全員でお別れをする時間を確保しましょう。特に小さなお子さんがいる場合は、愛犬の死について丁寧に説明し、一緒にお別れをする時間を作ることが大切です。
2. 遺体の取り扱いと供養方法火葬の手配
2.1. 遺体の一時的な保管方法
死後硬直までに遺体の形を整える
犬の場合、死後硬直が始まる前に身体を丸めた状態にしておくと、棺に納めやすくなります。また、目や口が開いたままの場合はそっと閉じてあげてください。
※数十分~数時間ほどで身体の筋肉が固まる死後硬直という現象が発生します。
遺体を清める
- 体を清拭し、好んでいたタオルや毛布等で包んであげて下さい。
- 腹部などから体液が漏れる可能性があるため、防水シートなどで保護。
- 保冷剤やドライアイスをタオルで包み、お腹の下に入れる(特に夏場は注意)。
棺の準備
棺としてダンボールやペット用棺を用意し、中に敷くタオルや毛布も準備してください。我が家では「天使のつばさ」という棺(袋形式)を購入しました。見た目も美しく、大切な愛犬との最後のお別れにはぴったりでした。(以下の写真)

我が家で購入した商品の詳細はこちら:
安置できる日数の目安
- 夏:1~2日
- 冬:2~3日
※気温や湿度によって異なるため早めの対応がおすすめです。
2.2. 供養方法の選択肢
①自宅で埋葬する場合
- 私有地であれば埋葬可能ですが、自治体の規則を確認してください。
- 深さ50cm以上掘り、他の動物に掘り返されないよう注意。
- 土に還る素材(布や木箱)で埋葬することがおすすめです。
②ペット霊園や火葬サービスを利用する場合
以下の方法があります:
(火葬サービス業者によって、表現が若干違います)
- 個別火葬: 1匹ずつ火葬し、遺骨を返してもらえる。
- 合同火葬: 複数のペットと一緒に火葬し、共同供養塔へ納骨。
- 移動火葬: 火葬車が自宅まで来て、近くの安全な場所迄移動して火葬しその後自宅でお骨上げ。
③火葬した後のお墓
- 合同火葬の場合は、他の犬骨と一緒に火葬業者が提携しているペット霊園に埋葬されます。
- 個別火葬、移動火葬の場合は、ご自宅にお骨が戻ってきますので、その後改めてペット霊園に埋葬することも可能ですが、ご自宅における墓石(ペットコティ)に納骨して、ご自宅での供養を選択される方が増えています。
④我が家の場合
我が家では、2012年に以前の愛犬「トーマス」が亡くなりました。火葬は「移動火葬」を選びました。火葬車で指定場所まで移動し、その場で火葬。その後、自宅でお骨上げを行い、骨壺は今でも自宅で大切に保管しています。


評判の良いペット専用火葬サービス5社紹介
| No | 会社名 | 対応地域 | URL |
|---|---|---|---|
| 1 | ペット葬儀110番 | 日本全国対応。24時間365日受付。 | https://www.petsogi-nabi.com/ |
| 2 | ジャパン動物メモリアル社 | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、宮城県、愛知県、北海道の一部地域。24時間365日受付。詳細は公式サイト参照。 | https://j-d-m.jp/area/ |
| 3 | なんさいがーでん | 埼玉県、千葉県、東京都、茨城県、群馬県、神奈川県、栃木県の全域。24時間365日受付。詳細は公式サイト参照。 | https://www.nansaikaikan.com/area/ |
| 4 | ペットの旅立ち | 日本全国対応。24時間受付。 | https://pet-tabi.jp/ |
| 5 | とわの虹 | 滋賀県全域。24時間受付。詳細な対応エリアと出張料は公式サイト参照。 | https://towanoniji.com/area.html |
各社の詳細な対応エリアやサービス内容は、上記URL(公式ウェブサイト)からご確認、見積もり依頼等できます。
火葬を依頼する会社を決めたら手配をしましょう。
3.役所への届出
犬を飼っていた場合は、市区町村の役所に死亡届を提出する必要があります(狂犬病予防法に基づく登録抹消)。各自治体のウェブサイトで確認しましょう。
👉 提出期限:死亡後30日以内
👉 提出方法:役所の窓口・郵送・オンライン(自治体による)
👉 必要書類:自治体によって異なるため、事前に確認
4.マイクロチップ登録情報抹消手続き
マイクロチップを装着している場合は、登録機関に連絡し、登録情報の抹消手続きを行いましょう。
尚、火葬は、マイクロチップが埋め込まれたままで可能です。
4.1. マイクロチップ情報登録先を確認する
日本では、マイクロチップの登録機関が主に以下の2つあります。
登録先によって手続きが異なるため、まずどちらに登録されているかを確認してください。
① AIPO(動物ID普及推進会議)
- 2022年6月1日以前に装着・登録された犬が対象
- 獣医師やペットショップで登録されたケースが多い
- 公式サイト:AIPO公式サイト
② 環境省 (犬と猫のマイクロチップ情報登録)
- 2022年6月1日以降に装着・登録された犬が対象
- ペットショップなどで購入した犬は、こちらに登録されている可能性が高い
- 公式サイト:環境省 犬と猫のマイクロチップ情報登録
4.2. マイクロチップ情報抹消手続きの方法
登録機関ごとに抹消手続きが異なります。
① AIPOの場合マイクロチップ情報抹消手続き
✅ 必要なもの
- 「登録事項変更申請書」(AIPOの公式サイトからダウンロード可能)
- 飼い主の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
✅ 手続き方法
- 「登録事項変更申請書」を記入(抹消理由に「死亡」と記載)
- AIPOへ郵送(FAXやメールは不可)
- 処理完了後、登録抹消通知が届く
✅ 手数料
無料(変更手続きのみの場合)
✅ 提出期限
特に期限の規定はないが、できるだけ早めの手続きが推奨される。
📩 送付先
〒107-0062
東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル東館8階
動物ID普及推進会議(AIPO)事務局
② 環境省の場合マイクロチップ情報抹消手続き
✅ 必要なもの
- 「変更申請書」(環境省の登録サイトからダウンロード)
- 本人確認書類
✅ 手続き方法
- 「変更申請書」に必要事項を記入(死亡を選択)
- オンラインまたは郵送で申請
- オンライン申請(マイページから手続き可能)
- 郵送申請(登録機関の指定住所へ送付)
- 処理完了後、登録抹消の通知が届く
✅ 手数料
無料
✅ 提出期限
こちらも特に期限の規定はないが、早めの手続きが推奨される。
📩 郵送先(環境省の登録機関)
〒103-0027
東京都中央区日本橋2丁目3-6 日土地日本橋ビル8階
マイクロチップ情報登録センター
5. 心のケアとグリーフサポート
5.1. 悲しみに向き合うことの大切さ
愛犬との別れによる喪失感から、不眠や食欲不振など心身への影響が出ることがあります。このような状態になった場合、自分自身を責めたり感情を抑え込んだりせず、「悲しい」という気持ちと向き合うことが大切です。
5.2. 家族や友人との共有
家族や友人と愛犬との思い出話を共有すると癒されることがあります。また、SNSやブログなどで気持ちを書き出すことで心が軽くなる方もいます。
5.3. 専門家への相談
必要であれば専門家に相談することも選択肢です。以下はペットロスカウンセリングサービスです。
6. 愛犬との思い出を大切にする方法
6.1. メモリアルグッズやアルバム作成
- 写真アルバムやフォトブック。
- 愛犬の毛や爪などを保存できるメモリアルボックス。
- オーダーメイドで作れるメモリアルジュエリー。
6.2. 新しい習慣を取り入れる
毎年命日にお花を飾ったり、お気に入りのおもちゃを飾ることで愛犬とのつながりを感じ続けることができます。
6.3. 次の犬を迎えるタイミングについて考える
新しい命との出会いは故愛犬への裏切りではありません。それぞれ大切な存在として受け入れる準備ができたら、新しい家族との生活も前向きに考えてみてください。
7. おわりに
大切な愛犬とのお別れは人生で最も辛い出来事の一つかもしれません。しかし、その悲しみは愛情深く過ごした証でもあります。一人で抱え込まず、大切な人たちと共有しながら少しずつ前へ進んでください。そしていつの日か、その悲しみさえも美しい思い出として語れる日が来ることを願っています。
もしこの記事がお役に立てたなら幸いです。また、ご質問やご意見があればお気軽にコメント欄でお寄せください。一緒に乗り越えていきましょう。
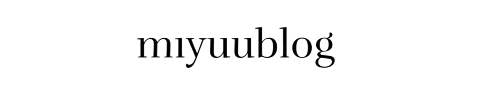




コメント